地球日記
三重大学 / 気象・気候ダイナミクス研究室の1コマ → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/earth/index.htm → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/
- 2025.11.16
2025気象学会秋季大会
- 2025.11.09
2025気象学会秋季大会
- 2025.10.03
雪氷研究大会@三重大学
- 2025.08.05
JPGU2025@幕張メッセ
- 2025.05.05
ACM(日中韓気象学会)2024@つくば
2025気象学会秋季大会
この文章は帰りの新幹線の中で書いています.車両内の子供の方の楽しそうにしている声が印象的でした.愛嬌という変数の第一モードは,対象との個人的な関係性なんだろうなと思います.
こんにちは,B4の永川です.11月の4日から8日にかけ,福岡国際会議場で行われた気象学会秋季大会に参加してきました.昨年度に様々な場所でお話を伺ってきたこともあり,今回はかなり上手に学会に参加できたのではないか,と考えています.細かな内容は以下に書いていこうと思います.読んでいただければ幸いです.
初日
初日は日ごろからお世話になっているJRA-3Qに関しての発表をいくつか拝見した後,台風に関してのセッションを聴講いたしました.私が研究室に入ったタイミングのあたりでJRA-55からJRA-3Qに切り替わったこともあり,今まではそれらの違いを今一つ理解していませんでした.今回の発表を通して境界値に関しての処理を始め解析期間の延長やバイアスの補正など,様々な改善点を具体的に知ることができました.また,これらの改善点が実際にどのような変化を及ぼすのか,といったことも期間の延長によって新たに調べられるようになったカスリーン台風の事例などを例に挙げていたことで,体感的にその内容を理解することができました.
台風に関するセッションにおいてはAIを用いた気象モデルによる台風の予測に関しての発表などがありました.AIを用いない場合での気象モデルに関しては,その予測精度が近年頭打ちになっているということも口頭発表で初めて伺いました.それはそれで面白い話だなと思う一方で,AIを用いることでその予測精度が飛躍的に向上することや,その結果に関しても一概にAIのみを用いることがより高い精度につながるとは限らないということが述べられており,気象予測にAIを用いることの面白さや難しさを垣間見ることができました.
その他にもセッション内では乱気流に関しての招待講演がありました.この講演においては,それまで大別されていた3つの乱気流とは異なる第4の乱気流である中層雲底乱気流に関して,そのメカニズムを丁寧に説明されていたことが印象に残っています.台風,乱気流ともに,私は普段あまり着目することのない領域の話であったため,今回の各発表を通して,それぞれどのようなことが各現象の基本となっているのか,またそれらのどの部分に着目して研究を行うのか,といったことなど,非常に多くの視点から発表を見ることができ,勉強することができました.
また,同日に行われた口頭セッション終了後の時間に行われた「地球観測衛星研究集会」という研究会にも参加してきました.普段身近にいながらもそれほどフォーカスが行われることのない,ひまわりといった人工衛星やJAXAといった宇宙関係の機関に関する話など,様々な話を伺うことができました.新型ひまわりについての話など,普段なかなか耳にすることのない衛星の裏側に関する話についてもたくさん伺うことができ,衛星だけに月の裏側を見ているような気分になりました.このような口頭後の研究会について,前回はその存在を知らなかったため,今回が初の参加でした.以前に立花先生が仰っていたようにラフな雰囲気であり,各発表の時間も比較的長く取られていたこともあって,話が聞きやすく,また訊きやすい環境でとても面白く感じられました.今後に関してはこのような会の情報を積極的に捉えていきたい次第です.
2日目
2日目の午前中に関しては,主に惑星大気に関してのセッションを中心に聴講していました.昨年度の気象学会においてはなんとなく木星や金星に関しての話題が多かった印象であったのに対し,今年度の気象学会においては火星に関しての話題が多かった印象がありました.昨日の台風などのセッションと同じように,ここでも口頭発表の導入部などを通して火星の惑星気象に関して大まかな内容を知ることができたため,非常に勉強になりました.火星には海がないことから,火星での大気の自由振動は日周期が支配的であるといったことは盲点かつ納得のいく話であり,地球の海の存在の大きさを改めて知るところとなりました.また,深層学習を用いたダストストームの擬似データの生成など,ローバーなどを通した画像データが少ない故の研究なども行われており,面白かったです.
3日目
この日は見たいものがたくさんある日だったので,少し気合を入れて参加しました.特に午後に関して,ポスターセッションにおいてはかねてから興味のあるブロッキング高気圧の渦位(PV)を用いた評価に関してのものを見てきました.何度かこの研究についてはお話を伺ってはいたものの,当時は渦位についてまだ勉強していなかったことや,ブロッキングの評価に関しての知識が浅かったことなどが理由で,内容をきちんと理解できていませんでした.それらを踏まえ,今回は自分なりに勉強や理解を重ねて臨みました.それが功を奏し,今回は内容を自分なりに理解することができ,PVを用いて評価を行うことの利点や解析結果から得られたブロッキングの特徴など,発表から多くのことを学ぶことができたように思います.「細かい構造を捉えることができる」というPV評価の特徴と,現在私が研究の対象としている擾乱については相性が良さそうであると感じられるため,どこかのタイミングで使ってみることができたらいいなと思っている次第です.
ポスター,お昼を経た後は「波と渦による気象・気候の見方」という名前の専門分科会に聴講で 参加してきました.このセッションにおいても学べることはたくさんありました.その中の一つが,「私が波とエネルギーに関する理解が非常に浅い」ということでした.今まではどこがわからないのかも今一つわからず,ショッピングモールで親を見失ったような心情になっていたのですが,今回やっとゲームセンターで毎回親がいなくなることがわかりました.自身の研究について考えるときのネックもここにあるような気がするので,この部分の力学についてもっと勉強していく次第です.
夕方以降も「第5回気候形成・変動機構研究連絡会」を聴講しました.メディアと研究者を交えた,リアルタイムでの対談というのは珍しく感じられ,興味を持って話を聞くことができました.話を聞いていて,パネリストの一人である川崎さんが仰っていた「スピード感」という言葉が印象に残りました.学会などに参加していると2021年や2023年など,数年前の現象が最近起こったこととして話され,私自身も知らぬ間にそう感じるようになっていたため,この話を聞いていた時に一般の方が捉えている「最近の」現象がどのようなものか,改めて気が付かされました.個人的にはこの部分はなかなか気が付きにくく,また重要な気がしたため,今後も意識していきたいなと感じました.また,もう一人のパネリストである伊藤さんが仰っていたことに関して,ラジオを通して言葉のみで天気を伝える方法の話が印象に残っています.「今,この場はどうなのか」,あるいは「最近冷え込んだ,気温も実際に5℃下がった」というように,言葉を用いてリスナーの方々に共感,ライブ感を与えることで,映像のないラジオという媒体で天気を伝える,という話を通して,コミュニケーションの新しい側面を知ることができ,とても面白かったです.
共感といったような感性はパネリストのお二方とも言及されていて,取材などにおいて話し手となる研究者がいかに楽しそうであるか,現象を示す言葉がキャッチーなものであるか,といったことなど,感性的な面でも取材対象が選ばれているということを知ることができました.私が今後発表を行う際も,このような部分を考慮した発表ができればいいなと感じました.
4日目
この日はお昼に会った他大の先輩から頂いた,研究に関してのアドバイスがとても印象に残っています.私の研究している黒潮や黒潮続流,ストームトラックに関する事柄について,参考になる論文やそれを踏まえた意見などを数多く,加えて私の疑問に対して非常に丁寧にご教授頂きました.また,論文に対して抵抗を持たずに読むコツなども教えて頂いたことで,その後に論文を読む際の精神的なハードルがぐっと下がりました.お昼という短い時間ではあったものの,得られるものが非常に多く,とても有意義な時間を得ることができました.
5日目(最終日)
この日は寒気に関するセッションをはじめ,ストームトラック,ジェット等に関する話題が午後にもちらほらとあるなど,最後まで気の抜けない一日でした.
中でも研究室の先輩が教えてくれた方の発表の一つが私の研究とよく似た方向性のものであり,私の研究とどのような点が似ているか,またどのような点では異なっていて,私の研究として示すことが可能であるかといったことなど,多くの面で非常に参考になりました.内容そのものも非常に面白く,大気海洋相互作用の面白さと可能性,また難しさを感じました.改めてもっと勉強していこうと感じた次第です.
各日の所感などはおおよそこのような感じです.この秋季大会全体を通して,個人的に一番大きかったことの一つは,遅くとも前日にはポスターや口頭発表のプログラムを確認して,どのような発表を見るべきか,あるいは見たいかといったアタリをつけておくことでした.至極当たり前であるという認識はあるのですが,やはりこれをするとしないとでは,どのような発表をより重点的にみるべきかといった体力配分のしやすさが全く違うように感じられました.今後はサボらずきっちり刷ってペンでグリグリしていこうと思います.
今回の参加での反省点としては,各発表の予稿に目を通していなかったことが挙げられます.発表中にサッと流されてしまった部分が気になってしまい,その後の内容についていけなくなったということがしばしばありました.それらの多くの部分は恐らく手元に予稿があれば解決できたように感じられるので,最低限「これには絶対に行く」と決めていた発表のものは目を通しておくべきであったなと感じました.
同じ学会であったにも関わらず,今回の参加では前回と比べて非常に多くの学びを得られるようになっていたことを強く感じました.僕の研究に関しても様々な方に論文の紹介やアドバイスを頂いたため,その厚意に応えられるよう,一層の努力を重ねていこうと改めて感じている次第です.この学会の後,そう遠くない来月の上旬にハビタブル日本全体会合や大気海洋相互作用研究集会などがあり,それにも参加をする予定なので,そこではこれらの反省を生かしていきたいなと思います.
最後に,私が博多で見かけたかわいいマスコットキャラを紹介させていただきます.
キューポちゃんというそうです.博多で3時間グッズを探しましたが見つかりませんでした.
今回は以上です.気がついたら4000単語を超えていました.書きすぎですね.
もう少しまとめるよう善処します.
長々と読んでいただきありがとうございました.
2025気象学会秋季大会
お久しぶりです〜天野です。
11月4日〜8日に開催された気象学会秋季大会@福岡博多 へ行ってきました。
面白い研究で頭と心を、美味しい料理でお腹を満たしてきました。
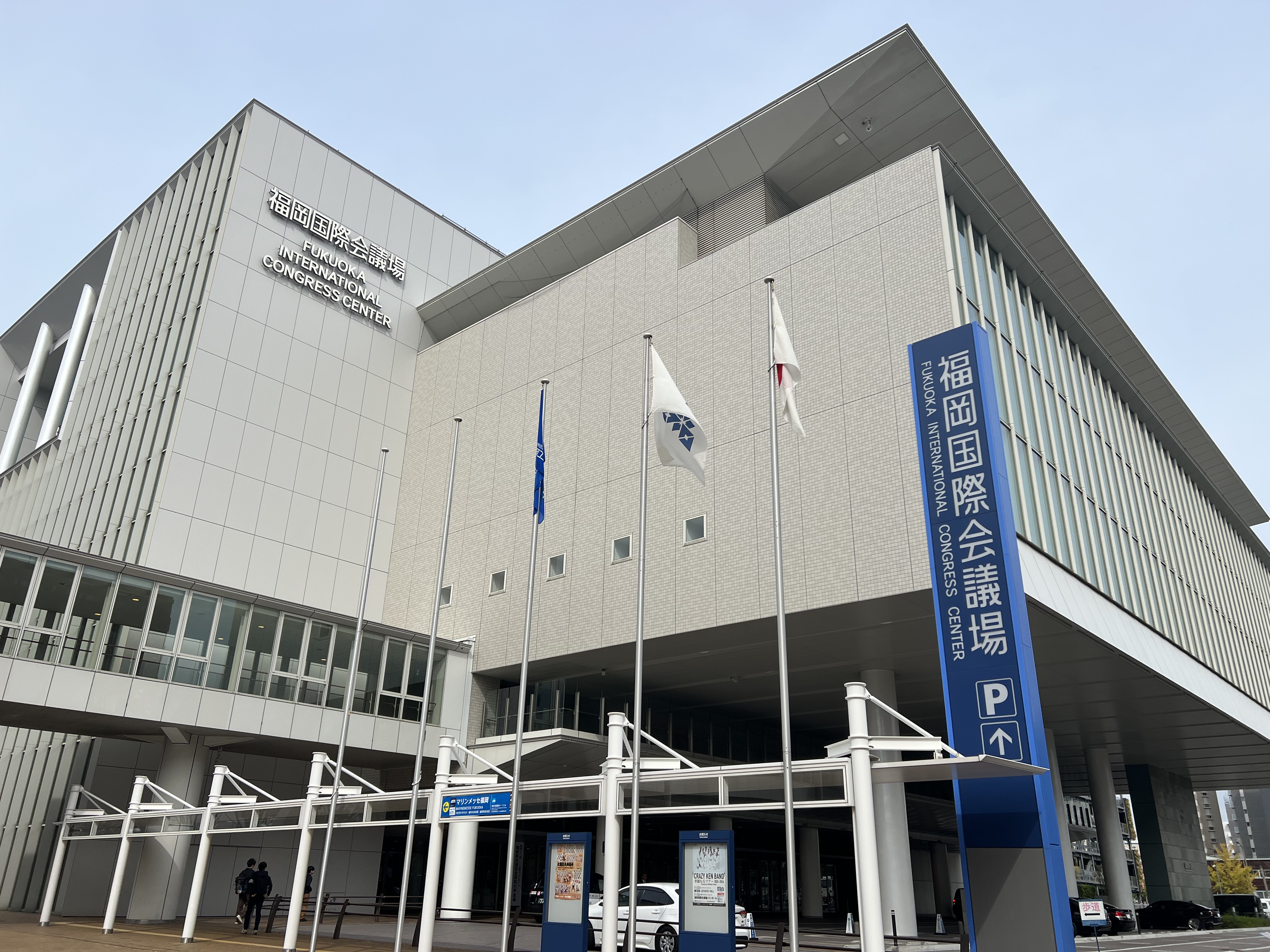
*****
発表聴講
気候システムセッションに加え、観測手法や大気境界層に関する話題も聞いて回りました。
特に、今回初めて聞いた、筑波大 日下研の学生さんらの笠雲、吊るし雲、滝雲等に関する研究が、すごく新鮮で面白かったです。観測とシミュレーションを組み合わせた、研究の流れや、シミュレーションの設定等が大変参考になりました。Xでの論文についてのポストもあった気がするので、あとで目を通してみよう。
加えて、最終日の専門分科会「2025年冬の大雪と低温がもたらしたマルチスケールからの要因分析と海洋熱波の影響」は、24/25冬季の話題に加え、25/26冬季についての総合討論も行われました。2月の帯広豪雪に関する話題が3件ほどあり、1つのイベントに対する解析の方法、解釈の仕方の違いなどが面白く、参考になりました。
気変連 https://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~iccv/
今回の気候形成・変動機構研究連絡会では、「気候変動情報の普及と気象災害への備え:マスメディアとの連携」をテーマに、立花先生、NHKラジオ気象キャスターの伊藤みゆきさん、静岡朝日テレビ記者の川崎豊さんとでパネリスト間対談と、参加者を交えた議論が行われました。
- ラジオで(声だけで)天気を伝える際の工夫
- 報道・取材する際の記者の観点(キャッチーさ、リアルタイムさ)
- 研究者側が思っていること
- 今後の学会とメディアとの関係やあり方、有効なイベントはあるか
などなど、活発に意見が飛び交いました。私も、ちょこちょこメディアに取材していただいている身として、日頃から感じていて共感できる話もあれば、初めて聞いたメディア側の事情や考えもありました。
現状、研究者とマスメディア、双方の歩み寄りや理解が必要な部分が多そうだと感じた一方で、普及・備えという目標に、二人三脚で歩める可能性が十分にあるとも思いました。
具体的な、共通の結論が出たわけではないものの、この議論が発生したこと自体に意味があるなと感じました。
*****
今回私の発表はなかったのですが、解析中の結果を、空いた時間に、共著者の方や、お声がけさせていただいた方に共有・相談させていただきました。1人で悶々としていた部分があったので、大変ありがたかったです。
加えて、久々に会う同期・先輩・後輩や先生方にも近況報告ができたことも、非常に嬉しかったです。
気象学会で得た情報を踏まえて、また明日からも頑張りたいと思います!
ではでは。

雪氷研究大会@三重大学
こんにちは、B4の濱口翼です。
同研究の教授である立花先生がここ1年程1か月に一回のペースでテレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショーに出演しているのですが、最近までリアルタイム以外で見る方法がありませんでした。しかし、TVerで過去1か月ぐらいは見れるようになったのでたまに先生が出演している回を見てみようかなと思いました。
さて、今回は9月7日~10日に三重大学で行われた雪氷研究大会に参加したのでその件について書いていこうと思います。今回は三重大学で行われたので会場運営のアルバイトをしながら聞いていました。
7日は公開講演会と雪氷楽会が行われました。雪氷楽会は雪や氷に関するワークショップで楽しい体験ができるイベントでした。また、公開講演会は東海地方のテレビに出演している気象予報士の方が集まり、研究者の方と雪について語るというイベントでほかの学会の公開講演会よりも一般の人が参加しやすいイベントであったと思いました。
8日から10日はほかの学会と同様に研究発表が行われました。ここからは、特に面白かった内容2つを少し紹介します。
1つめは、そろばん道路です。そろばん道路冬の北海道などの雪国で路面に氷のコブが多数発生した状態の道路のことで発表者はどのような条件でそろばん道路ができやすくなるのかについて実験した内容を発表していました。現象としても発表の内容としても大変面白く、アルバイトとして普段聞かない工学のセッションにいてもこれだけは前のめりになって聞いていた内容であったなと思いました。
2つ目は、ドカ雪のセッションです。近年多発する短時間にたくさんに雪が降ることをドカ雪と呼びその現象についての発表が行われたセッションでした。冬の気象現象やそれに伴う影響についての発表が多く、どの発表も惹かれる内容が多かったです。このセッションは夕方に分科会が行われたのですが、それにも参加しさらに深い議論が行われ、それも大変面白かったです。
雪氷研究大会は三重大学で開催されない限り、参加しないであろう大会ではあったので知見を広めるうえで参加してよかったなと思いました。特に工学分野のセッションは学会に参加したとしても見に行かないであろう分野であったので知らないことをたくさん知れてよかったなと思いました。また、時間とお金があったら自分の分野とは少し遠い分野の学会にも参加してみたいなと感じました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
JPGU2025@幕張メッセ
お久しぶりです.B4の永川です.
先日,「族長の秋」という小説を読みました.ある国の独裁者の孤独な在り様が独特な文体で示されており,非常に良い体験をすることができました.とても面白かったです.
そんなことはさておき,5月末頃に東京幕張メッセで行われた日本地球惑星科学連合,通称JPGUに行ってきました.先輩から「地学のコミケ」と称されるほどに様々な発表などが伺えることを聞いており,大きなわくわくを胸に参加してきました.その報告を行わせて頂きます.
今回のJPGU参加においては5月26日から5月29日あたりまでの発表が気象に関わる分野を多く取り扱うものであり,私自身もその部分に集中して参加を行えるようなスケジュールで伺いました.25日などにも参加はしていたのですが,口頭発表については英語で馴染みのない分野の発表が行われており,なかなかな難しさを感じました.ただしポスター発表については日本語で解説を行って頂いたことなどもあり,自身の知らない分野についても理解を深めることができました.火星などでの居住を想定した閉鎖空間での生活に関しての実験や,教育的な側面を持つボードゲームの製作の過程に関しての観察実験など,普段は見ることがないものの,内容としては非常に面白いものが多く,とても面白かったです.
2日目以降については非常に内容が多く,実のある時間を過ごすことができました.まず大きな学びとして挙げられることはやはり黒潮大蛇行セッションや中緯度大気海洋相互作用セッションの口頭発表の聴講です.僕自身が黒潮大蛇行に係る大気海洋相互作用に興味があったこともあり,このセッションでの発表は非常に楽しみにしており,また実際に聴講を通して黒潮や大気海洋相互作用について自身の知見をより深くすることができました.特に次世代衛星高度計ミッション,通称SWOTに関しての発表については,SWOTそのものや,発表内で話されていた,大きく蛇行した黒潮から発生した断水塊の西進に伴う新たな大蛇行の発生の仕組みなど,僕にとっては初めて見聞きするものでありながらも,内容もある程度理解できるものであり,非常に面白かったことが印象に残っています.黒潮大蛇行に伴う東海,関東沖の沿岸昇温に関する発表についても,SSTの上昇に伴って発生する降水の増加や気温の上昇についての解説が非常にわかりやすく,勉強になりました.英語の発表についても自身に馴染みのある分野であったことが幸いし,今までは全体を通してさっぱりだったものが,今では適宜単語が聞き取れるようになっており,内容も最低限は捉えられていたので成長を感じることができました.気のせいかもしれませんが,英語での発表(というよりも外国の方の発表?)では,北半球での海表面塩分の季節変動など,日本語でのものと比べスケールの大きな研究が大きいように感じられました.このセッションにおいては自身の興味のある分野であるだけに,私が以前読んだことのある論文の著者である方なども多くいらっしゃっており,その面でも感慨深いところがありました.
口頭発表のみならず,ポスター発表や企業ブースなどでも様々な話を伺うことができました.ポスターについては口頭発表以上に自身の興味に任せて話を伺うことができたことに加え,自身の疑問をたくさん発表者の方に問うことができました.これらを通して僕の研究活動に向けておすすめの論文を紹介して頂くなど,様々な形でアドバイスなども頂くことができ,非常に大きな学びとなりました.企業ブースについても想像以上に多くの企業が参加していたことに加え,話を伺った際,どの企業の方もとても丁寧に発表内容の解説をして頂いたことがとても強く印象に残っており,私の1の質問に対して10や100の回答をして頂き,とてもうれしかったです.
初参加,しかも慣れない関東での開催ということで初めは緊張の連続でしたが,実際に参加した後からは駆け抜けるような5日間だったように感じます.ここで書いたことの他にも様々な方とお話をさせて頂き,非常に有益な情報を教えて頂いたことや,期間中に行われたセミナーに参加したりなど,本当にたくさんの,かつ貴重な経験をすることができました.
来年も可能性があればぜひ参加したいと思います.
ここまで読んで頂きありがとうございました.
ACM(日中韓気象学会)2024@つくば
今回は11月18日から20日まで,つくばで開催された「2024年 日中韓気象学会」について書きます.
今回はここまでになります.読んでくださりありがとうございました.
リンク
カテゴリー
最新記事
最新コメント
ブログ内検索
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
プロフィール
共生環境学科
地球システム学講座
気象・気候ダイナミクス研究室です。
・普段は興味のある気象・気候について研究しています!!
・研究室への質問疑問などなどがありましたら、コメントでも拍手でも構いませんので遠慮なくカキコお願いします!(^0^)ノ





